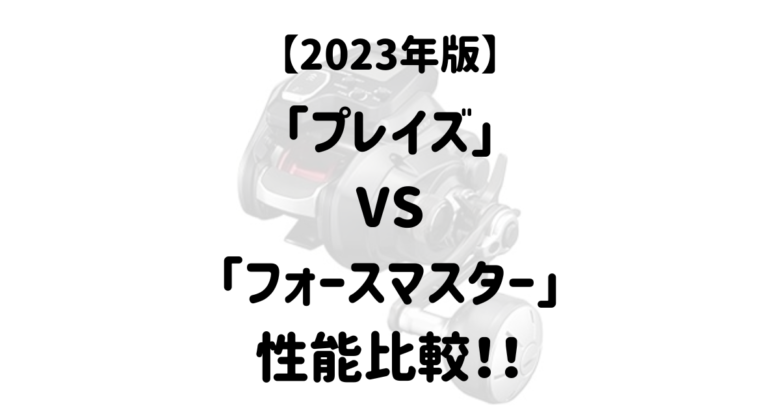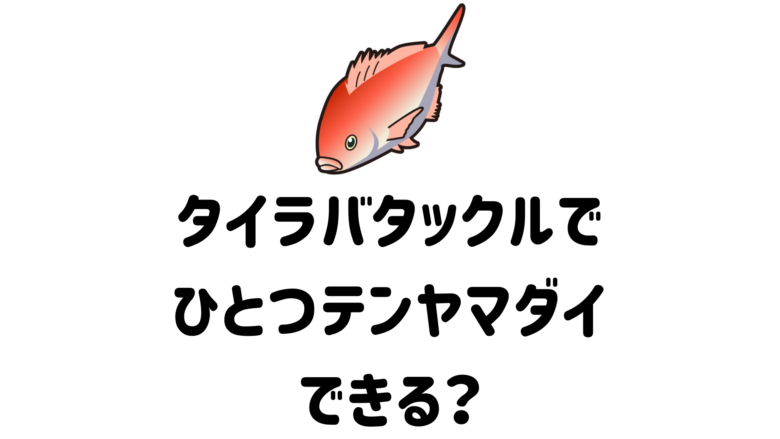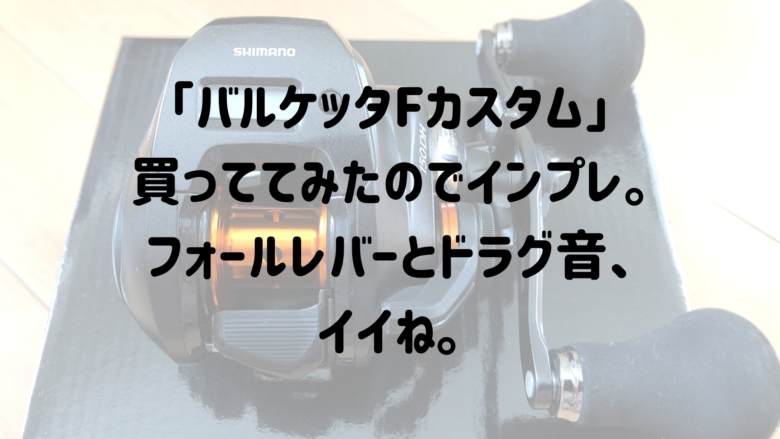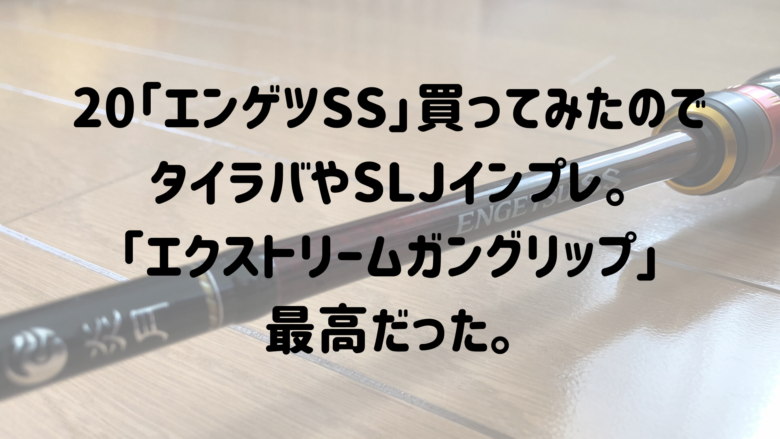タイラバロッドは軽いほどイイのか?メリットとデメリットを考えてみた

タイラバロッドが軽量であることの重要性
本記事ではタイラバロッドの自重について少し語りたいと思います。
例えばブラックバスやシーバス、エギングロッドなどではキャスティングやアクションが必要であるためロッドの軽量さは重要である、というのは共通認識。
ロッドが重いとキャスティングしにくいし、シャクッたりアクションし続けるのも疲れますから軽いほうがイイとよく言われます。

一概に軽ければ軽いほどイイ!という訳ではありませんが
ではキャスティングもアクションも必要とせず、基本「落として巻く」というタイラバにおいてロッドの軽量さはどれほど重要なのでしょうか?
今回はタイラバロッドが軽量であることの重要性をメリットとデメリットをあげて考えてみたいと思います。
軽量タイラバロッドのメリット
まずはタイラバロッドが軽量であるメリットから。
感度がよい
軽ければ軽いほどロッドの感度は良くなります。

とはいえ一概に軽ければ軽いほどイイ!ってことでもなく、ロッドの重量バランスなどにも左右されます。
理論上、重さ以外の素材や長さなどの要素をまったく同じ条件にした上で軽いロッドと重いロッドを比べると、軽いロッドの方が「相対的に」感度が良いということですね。
(素材も長さもまったく同じで違う重量のロッドが作れるのかどうかは分かりませんが…)
タイラバではキャスティングやアクションは基本的に必要ではありませんが、逆にただひたすら巻き続けて小さなアタリをとることに集中する、というごまかしの効かない繊細な釣りであります。
他の釣りでも感度は重要ですが、特にタイラバにおいては小さなアタリをいかにとれるかで釣果を左右するため、タイラバロッドは感度が命!といってもいいのでしょう。
疲れにくい
ロッドが軽量だと当たり前ですが疲れにくいです。
アクションは必要ではない、とはいえ基本手持ちでリールを巻き続けるタイラバ。
ずーっと同じ姿勢で持ち続けるわけですから、少しの重量の違いでも1日通してやってると疲労度は大きく変わってきます。
リールの重さも関係してくることではありますが、「軽い方が疲れにくい」というのは間違いないでしょう。
集中力が持続する
上記に関連してきますが、ロッドが軽量で疲れにくいと集中力が持続しやすい。
逆に考えるとロッド(とリール)が重いと疲れやすく、集中力も落ちてきます。
良く釣れたり、アタリが頻繁に出続けていれば多少の疲労があってもテンションでカバーできますが、そうではなくアタリもない渋い状況の時。
集中力が落ちてくると、
「あー、疲れたなー…」
「釣れないし、飽きてきたなー…」
「今日の晩飯何食べよっかなー…」
みたいに別の事を考えてしまいます。
そんな時1日に1回あるかないかのほんの小さなアタリを逃してしまい、フォールに移行してしまったり巻き速度が変わってしまって見切られる→結果ヒットに持ち込めず…
なんてこともあり得るわけです。てか結構あるハズ。

タイラバという釣りは(特に渋い状況の時は)一瞬も別の事を考えたり、気を抜いたりせず、集中して取り組まなければいけない修行のような釣りなのであります(笑)
まあ半分冗談ではありますが、ロッドが軽い→疲れにくい→集中力持続で釣果につながることは間違いないでしょう。
軽量タイラバロッドのデメリット
続いてタイラバロッドが軽量であることのデメリットをあげていきます。
剛性、強度が劣る
これもロッドに使われている素材や技術(金属の穂先やカーボンテープをクロスに締め上げるなど)にも左右されるため、一概に必ずしも「ロッドが軽い=剛性、強度が劣る」というわけではありません。
しかし、強度や剛性を上げる素材を使ったりするとその分自重が重くなるのは事実。
強度や剛性を上げるためには自重が重くなる、ということで相反する項目でありますが、うまく両立させるために結局はバランスが大事なのでしょう。
高額なロッドであるほどこの強度や剛性と自重のバランスがうまくとれるよう設計されています。
バランスの問題
先ほどの自重と強度、剛性の関係以外にも注意するバランスがあります。
例えばロッドのグリップ部と先端とのバランス。
一般的にはグリップ部より先端の方が細くて軽いのは当然ですが、そのバランスによってはロッド全体の自重以上に重く感じたりする場合もあります。
例えば全体の自重が同じで、グリップ部が軽いロッド(先端が重い)と重いロッド(先端が軽い)2本あるとします。
この2本のロッドを比べると、グリップ部が軽く先端が重いロッドの方が重く感じるハズ。
しかしもちろんカタログ上ではその重量バランスなんてものは記載されておらず、感覚的なものなので実際に持ってみるのが一番でしょう。

結局は高額なロッドほどバランスよく仕上がっていることがほとんど
ほかにリールとのバランスや使用するフィールドにもよります。
潮流が速かったり超深場などのポイントだとパワーがある重めのリールを使用する必要がある場合もあるでしょう。
この場合ロッドはメッチャ軽いのに、リールが重すぎるとせっかくの軽さが活かせませんし、使用するタイラバの重さともアンバランスになりそう。
この辺は軽量ロッドのデメリットとはちょっと話が逸れてきて余談でしたネ。
予算の問題
単純にとにかく軽量なロッドを!と探すと例えばダイワ「紅牙X」のように安いモデルが該当します。
ただ、使われている強度や剛性を上げる技術や素材が上位モデルと比べると少ないです。
そのため、強度や剛性を犠牲にして軽さと安さで勝負しているわけですね。
じゃあその強度や剛性も、となると結局高額な上位モデルを選択せざるを得ない。
予算の関係で上位モデルの購入が難しいのであれば、安いモデルの弱点を理解して使い手がカバーしながら使う必要があります。
まとめ
以上軽量ロッドのメリットとデメリットをあげてきました。
タイラバにおいてロッドは単純に軽ければ軽いほどイイということではなく、強度や剛性、バランスの問題も絡んでくるということでした。
- 軽ければ軽いほど一概にイイ!というわけではない
- しかし釣果につながるすごく大事な要素
- 強度や剛性もあって軽いロッドは高額
もちろん軽さというのは釣果に直結するほど重要な項目ではありますが、強度、剛性、素材や予算などのバランスを考えて選択する必要がある、ということですね。

わしゃ金持ちじゃけ予算はナンボでもOKじゃ!
っていう方はダイワでもシマノでも最上位モデルを選択すれば間違いないでしょう。
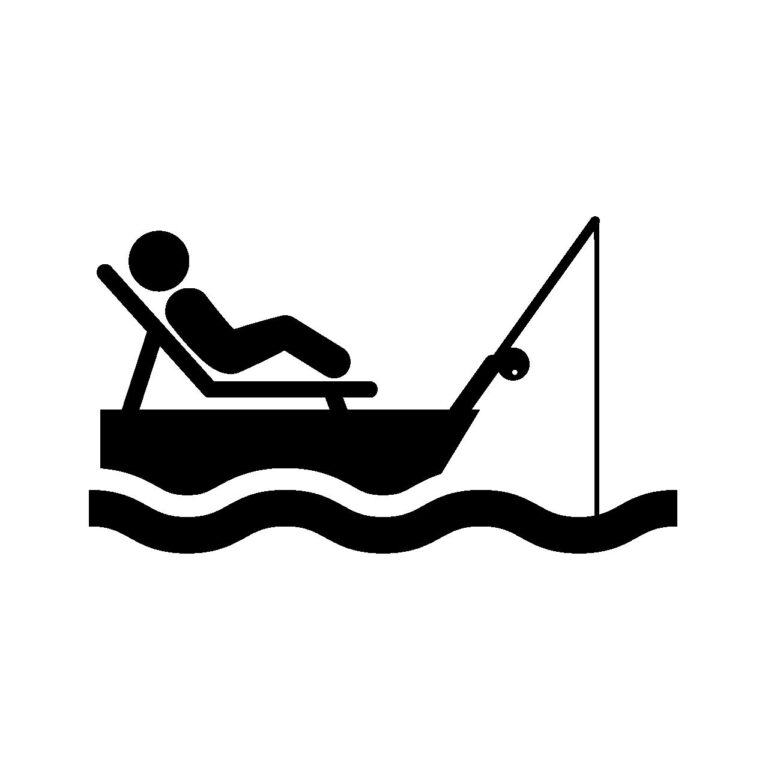
予算は1万円!とにかく軽量ロッドで勝負!あとは腕でカバー!
なんていう男前の方にはあとでオススメロッドをご紹介します。
以上タイラバロッドにおいて軽量であることは重要!というお話でした。
予算に合わせてうまく軽量ロッドを選んで、よりタイラバを楽しみましょう!