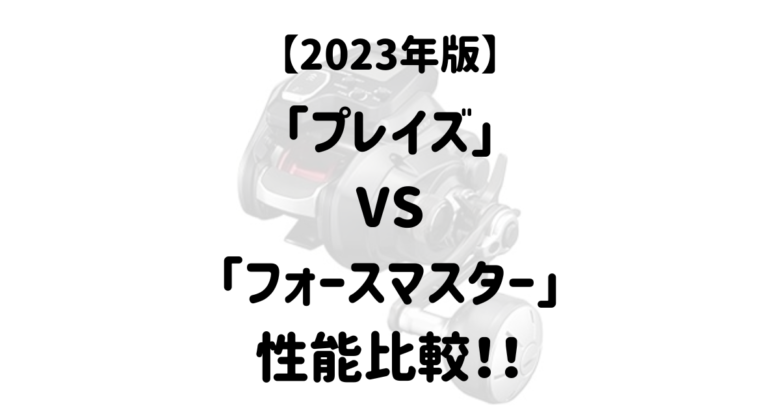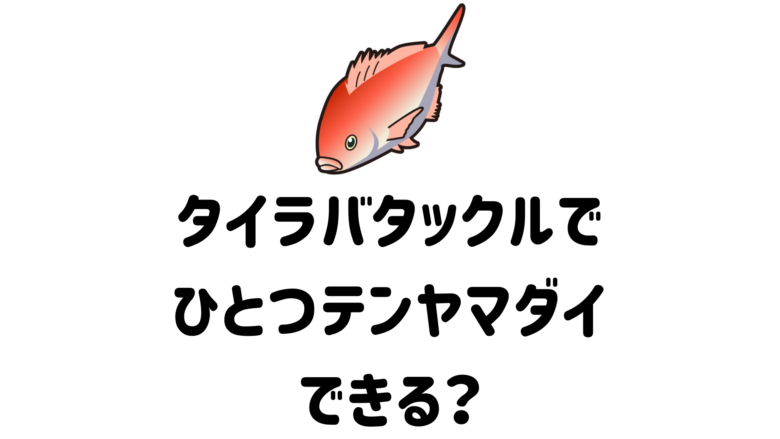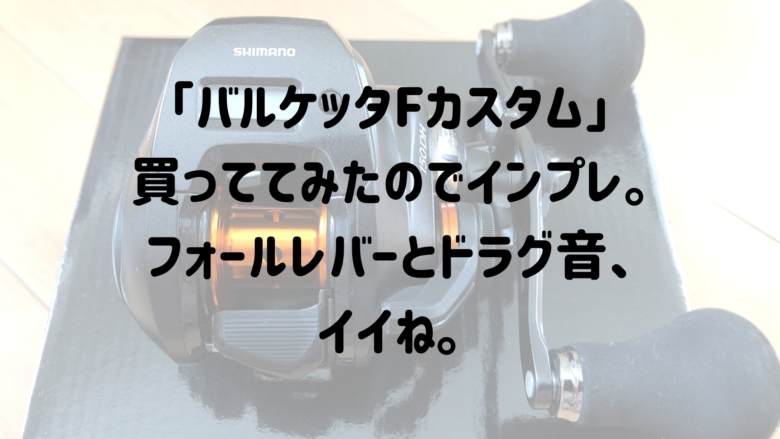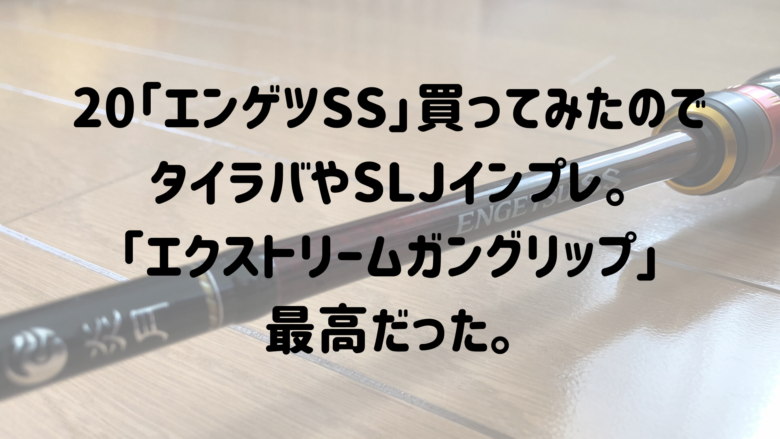タイラバロッドの選び方。カタログからロッドの特性を読み取ろう。
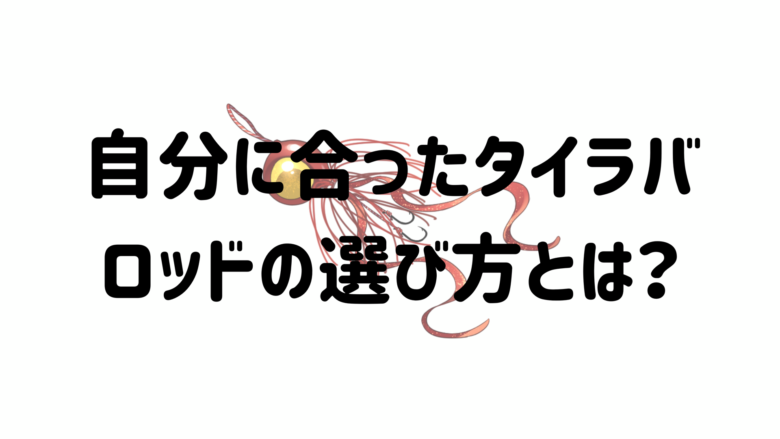
タイラバロッドの選び方

タイラバロッドを買おうと思うんだけど、種類がいっぱいでどう選んでいいかわかんねーな…

カタログ上の適合ルアー重量やラインの太さとかは自分が使うタイラバやラインに合わせればOKっていうのは分かるよね?

うん、なんとなく。

あとは”チューブラーとソリッド”とか”カーボン含有率”とか”自重””先径”…といった項目もある。これらからそのロッドのある程度の特徴が分かるんだ

ってことで今回はタイラバロッドを選ぶ際に参考になる、カタログの項目の読み取り方を解説しよう

よろしく!
チューブラーとソリッド
まず竿先の構造、チューブラーかソリッドか。
チューブラー(tubular)とは「管状、円筒状」という意味で、直訳通りロッドの中が空洞になっている構造。
一方ソリッド(solid)とは「固体」、「 固体状であること」という意味から、竿先の中身までカーボンを主とした素材がぎっしりつまっている構造です。
ではそれぞれのメリット、デメリットを簡単にまとめてみます。
- 中空構造のため軽量
- 張りがあるためキャストやルアー操作がしやすい.
- 中空構造のためロッドの径が太くなる
- 張りがあるためアタリを弾きやすい
- 中身が詰まっているため細くできる
- 粘りがあるためアタリを弾きにくい
- 細くできるけど、剛性が落ちる
- 粘りがあるためキビキビしたルアーアクションなどは苦手
以上のように相反する特性を持っています。
タイラバに以上の特性を当てはめて簡単にまとめるとこんな感じ。
自分に合った釣りに合わせて選択すればOKですね。
タイラバにおいては穂先の感度がかなり重要で、逆にキャスティング性能やルアーアクションをさせる操作性がそこまで求められていない、ということから「乗せ調子」特性のあるソリッド構造が主流であります。
このソリッド構造により極端に先径を細く仕上げることができ、モデルによっては1mmを切る細さの物も。
そしてこの細さから高感度を得ることができるため、タイラバロッドの主流になっているのでしょう。

現にダイワやシマノはほとんどのタイラバロッドが(「掛け調子」モデルでも)ソリッド構造になってますね
さらに最近はロッド製造技術の発達によりそれぞれの短所を補えるようにもなってきています。
例えばソリッドは中身が詰まっているため重くなるというデメリットがありましたが、薄くて強いカーボンシートを巻きつける方法で軽量化!!など。
ということで、昔からロッド選びにおいて永遠のテーマとなっているチューブラーとソリッドどちらがいいのか!?という問題、ことさらタイラバロッドにおいては個人的にはソリッド向きと思います。
素材 「カーボン」と「グラス」と「チタン」
続いて素材。
各メーカーのタイラバロッドはほぼカーボン+若干グラス素材でできているものがほとんどです。
カーボンとグラスの割合はカタログ上の「カーボン含有率」という項目を見ると分かりますが、タイラバロッドのほとんどが90%以上カーボンが主流になっています。
ただ、中にはカーボンが80%台でグラス割合が多いロッドもありますが、グラス素材割合が多いとどうなるのでしょうか。
グラスとは一昔前に主流だったロッド素材で、現代となっては重く、感度も弾性も劣るものです。
重くて感度が悪いのはどうしようもないですが、弾性が劣るということは良く言うと低弾性(反発力が弱い)でアタリを弾きにくい柔軟性があると言えます。
タイラバにおいては、タイラバがスカートなどをついばんでいる時、弾性が高いロッドだと反発力が強く、鯛に違和感を与えてバラシてしまう原因にも。
一方低弾性のロッドだと、スカートが引っ張られる動作に応じてゆっくり曲がり、それに対して反発して戻る動作もスローであるため鯛に違和感を与えにくい、つまりバラシにくく乗せやすい。
グラス割合が多いロッドはこのバラシにくいという長所がより活かされているということですね。
他にはダイワの「スーパーメタルトップ」のように穂先がチタン製のものもあります。
このチタン製の長所は、金属製であることからとにかく感度に優れるということ。
魚のアタリに対してロッドの穂先の振動の増幅力がほかのカーボン素材などと比較して圧倒的に強く持続することで、手元にも伝わってきやすくなっています。
また金属であるため、カーボンなどと違い簡単には折れにくいということもメリットです。
逆に短所としては、少し高価であること。
また金属のため簡単には折れませんが、気温によっては穂先が曲がったまま自然には戻らない現象が起こることも。

手でゆっくり逆方向に曲げると戻りますが、頻繁に行うと金属疲労の原因になるため注意が必要
長さ
タイラバロッドは各メーカ6.9ft(約2.1m)前後のものが主流。
ただ中には6ft(1.8m)ほどの短いロッドから7.9ft(2.4m)の長いロッドもあります。
ではタイラバにおいてこの長さはどう選ぶべきなのでしょうか。
一般的に長いロッドをボートで使用する長所と短所は以下の感じ。
長所
- キャスト時に飛距離がでやすい
- アタリに対してノリが良い
- サビキなど長い仕掛けだと取り込みしやすい
短所
- 取り回しがしにくい(特に小さいボート)
以上のようにボートでロングロッドを使うメリットは多数ありますが、タイラバでは飛距離と長い仕掛けを取り込みやすいというメリットはほぼ関係ありませんね。
ロングロッドのノリの良さは武器ですが、アンダーハンドキャストするならショートロッドの方がしやすかったり取り回しが良いです。
って考えてると難しくなってきますが、ロッドの長さがルアーアクションにも影響するジギングやエギングに比べて、ただ巻きが基本動作のタイラバにおいてはロッドの長さ選択はそこまで神経質にならなくてもOKでしょう。
とはいえ簡単な選び方としては、ロングロッドならではのノリの良さはタイラバの大きな武器になると思いますので、普段乗るボートのサイズ(手元と海面までの距離)に合わせてできるだけ長いものを選択するのが一番よいかと思います。

いろんなボートに乗ってると、結局なんやかんやで主流である6.9ftぐらいが最もしっくりきて万能だったり
1ピースと2ピース
タイラバロッドは継ぎ目がないロッド(1ピース)とグリップ部やロッドの中央部分で分かれて2本になるロッド(2ピース)があります。
2ピースロッドは持ち運びがしやすい反面、継ぎ目に砂や異物が入って破損の原因になったりすることもあるため、釣りのことだけを考えると極力1ピースが望ましいです。
ただこれもそこまで神経質にならなくても大丈夫で、大きい車などで持ち運びできるスペースの余裕があるなら1ピース、電車移動や車内が狭いなどであれば無理せず2ピースの選択でOK。
無理に1ピースロッドにして、長いがゆえに車内などで穂先が折れたりすると本末転倒ですからね。
自重
タイラバロッドにおいては軽さは重要な要素です。
例えばシルエットが小さなタイラバにしか反応しない時があります。
そんな時は軽くて小さいタイラバを選択しますが、タイラバだけ軽くてリールやロッドは重くゴツイものを組み合わせるとバランス悪く、感度も落ちてしまいます。
そのためリールやロッドも軽量にし、ラインも極力細くすることで小さいタイラバともバランスがとれて感度も上がります。
ということでそんな状況でタイラバロッドに求められるのは軽量であることです。
軽量である反面、剛性や耐久性はどうしても落ちてしまうので、軽いタイラバを使用することが求められる状況がない場合は無理に軽量なロッドを選択する必要はそこまでありません。
それにタイラバロッドとして謳われているロッドの中では重いといわれるものでも、ほかの釣り竿全般の中では軽い部類に入りますので、1日釣りして持ち重りするようなものでもありませんから。
先径、元径
これは名前の通りロッドのもっとも先の外径(先径)とロッドのもっとも太い元部の外径(元径)のこと。
先述のチューブラーとソリッドという構造に大きく関係してくる数値で、比較的ソリッドの方がチューブラーに比べて構造上細く仕上げることができます。
タイラバロッドはソリッドが主流で、特に先径がほかの釣種用ロッドに比べてかなり細い部類。

先径が細いとどういうメリットがあるの?
まずは先径(穂先)が細いほうが感度が良いです。
魚のアタリや潮流の変化などが穂先に伝わり穂先が動く=アタリがあった、という情報は先径が細い方が入りやすくなるため。
それが手元まで感覚として伝わってくるかどうかはロッドの素材なども影響してくるので、細いから必ずしもそうだとは言えませんが、比較的伝わりやすいのは間違いないでしょう。
逆に先径が細いと強度や剛性、大物とのやり取りが不安です。
大物とのやり取りについては、タイラバロッドはロッドの中央から根元にかけて強度を持たせることで細い先径をカバーしています。
感度の良い先径の細い穂先で鯛の小さなアタリをキャッチし、魚を掛けた後はこのロッドの強い部分を活かしてやり取りができる、という設計ですね。
強度や剛性については、素材の項でもお話ししたように最近は穂先が金属製のロッドがあったり、最新カーボン素材と設計によって細い穂先でも強くなってきています。
ただ、どうしても先径が太いロッドと比較すると構造上弱いのは仕方ありません。

使用方法、移動方法を工夫して傷をつけないようにしたり、折れてしまわないように気を使って使用しましょう
タイラバロッドの選び方まとめ
以上タイラバロッドを選ぶために必要な、カタログに表記されている代表的な項目について解説してみました。
いずれの項目においても「絶対にコレが良い!」というのはなく、長所短所があるものです。
カタログをじっくり読んでいろんなロッドを比較してみるとそれぞれのロッドの特性は大体読み取れる部分が多いですが、実際は使用してみないと分からない部分もあります。
個人的には自分が最も重視する部分が優れているロッドを選択するのがオススメ。
例えばとにかく感度が良いロッドで小さなアタリをとりたいというときは、先径が究極に細くて自重が軽いようなロッドを選択します。
で、実際にそのロッドをもって釣行すると、感度に関しては最強だ!という思いがあるため釣りに迷いがなくなります。
逆にロッドに対して感度が良くないという不安があると、釣り方にもそれが表れる気がします。
ですから、各項目で自分が最も重視する部分がもっとも優れているロッドを選択しておけば自信を持って釣りができますし、次回のロッド選びの基準になりやすいです。

とはいえ必ずしも高額である必要もないと思いますので、予算の範囲内で選択できるベストなロッドを選んでみましょう!
カタログの項目をじっくり読んで、自分が普段行くフィールドや自分のしたい釣り方にあったロッドを選んでみましょう!