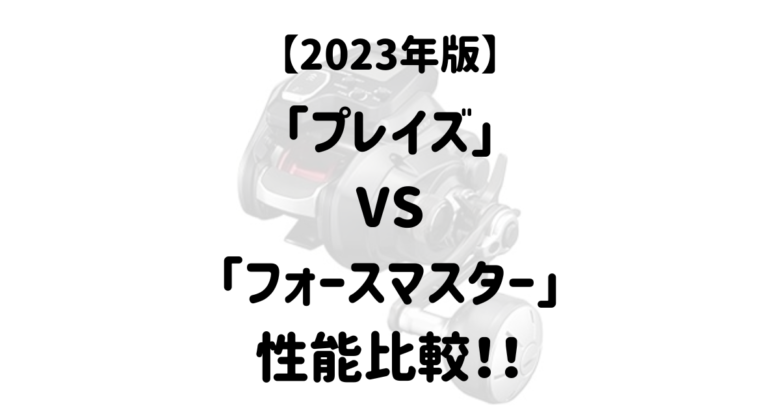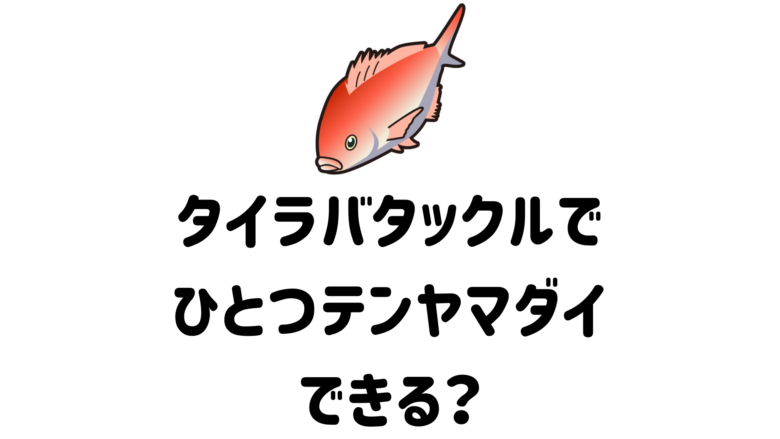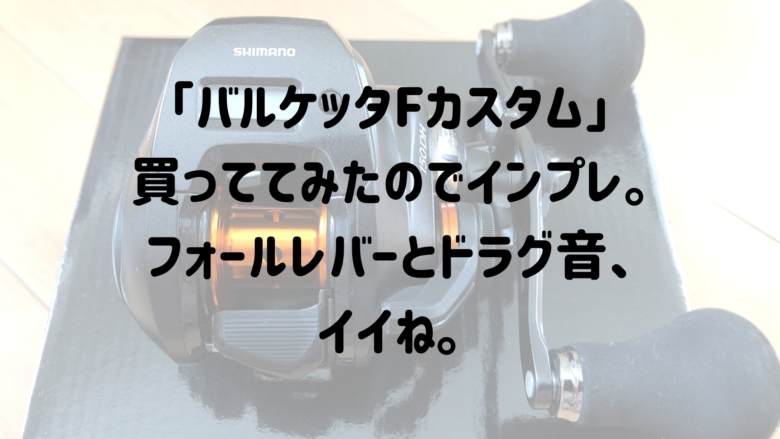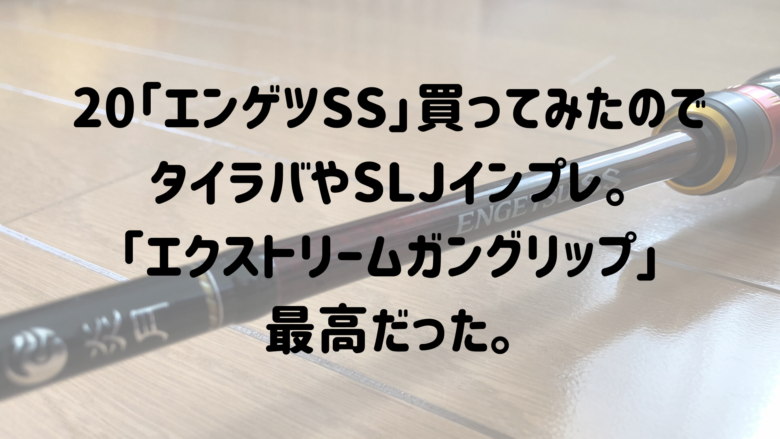ライトジギングタックルでタイラバはできるのか?兼用にオススメロッドとリール紹介も。
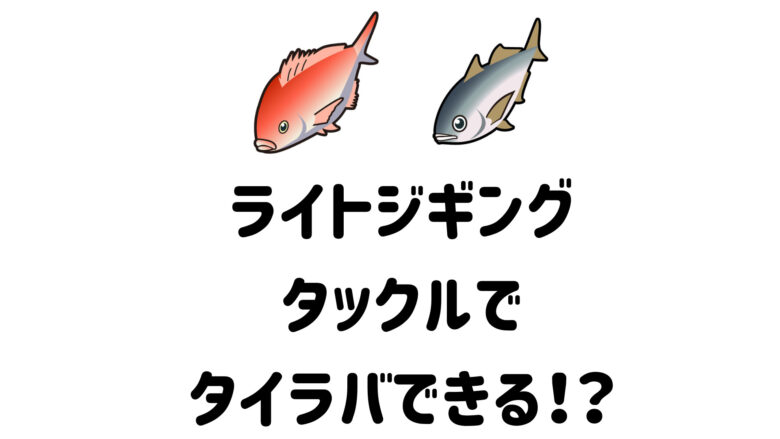
ライトジギングタックルを流用してタイラバやってみよう!

ライトジギングずーっとやってるけどアタリがなくて飽きてきた、そして疲れてきた…
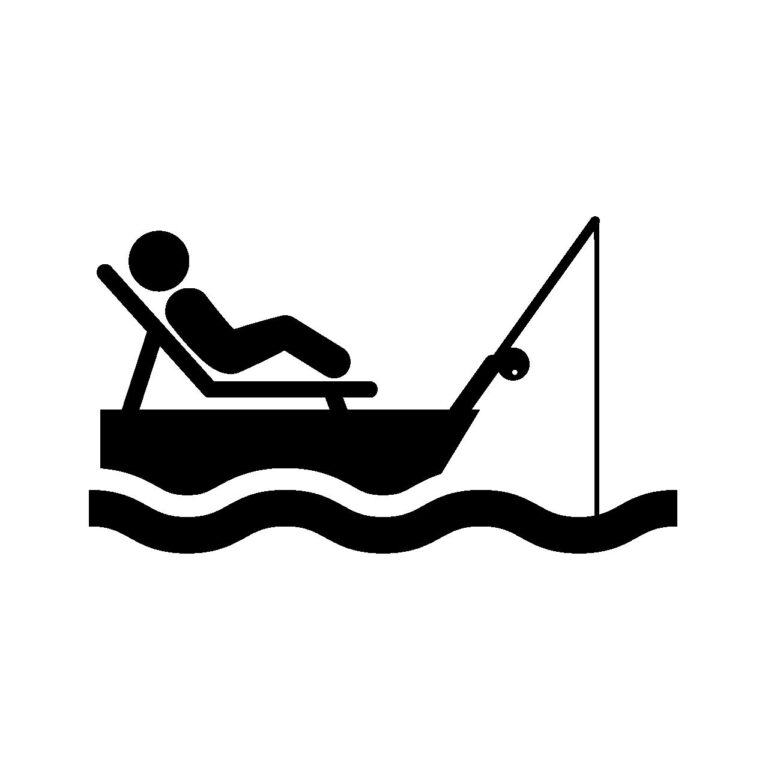
真鯛がいるポイントだけどジグに一切反応がない…タイラバやってる他船はメッチャ釣れてるやん!
ライトジギングメインで出船するも厳しい状況、アタリがなくてこんな風に思う事きっとあるはず。

釣れようが釣れまいがジギング1本勝負!渋い状況でもジギングにこだわって魚を引きずり出すことに命かけてまっせ!
こんな男の中の男であればほかの釣りに浮気することもないのでしょうが、やはり別の狙いの魚とは言え釣れるなら釣りたい…というのが本音では。
お土産に魚を持って帰らないといけない…っていう家族思いのジギンガーにも是非読んで頂きたいタックル兼用シリーズ。
今回はライトジギングタックルを流用してタイラバをやってみよう!っていう話です。
ライトジギングタックルとタイラバタックルの違い
まずライトジギングタックルとタイラバタックルの違いについて。
まず今回の話の前提として以下注意点があります。
- ともにスピニングモデルもあるけど、今回はベイトモデルの話
- 「ジギング」ではなく「ライトジギング」
タイラバはキャスティング対応、またジギングもキャスティングやハイピッチジャークなどに対応しやすいスピニングモデルもありますが、今回はともにベイトモデルに限って比較しています。
どこからどこまでが「ライトジギング」という明確な定義はありませんが、一般的には100g以内のジグを使用するジギングといったイメージ。
あるいは最近流行のスーパーライトジギングと呼ばれる30gとか40gといったもっと軽いジグを使う場合もあるでしょうが、どちらにせよ軽いジグを使用するのが「ライトジギング」。
本家「ジギング」は例えば200gオーバーのジグを使用することもあったり、対象が10kgオーバーのブリやヒラマサ、場合によってはマグロなんてことも。
これらを含めるとタイラバとはまったく違う釣りでさすがに兼用は難しい、ってことで今回は「ライトジギング」に限っております。
ロッドの違い
まずライトジギングとタイラバのロッドの違いについて一般的なスペック比較。
全長
- ライトジギング:約6~6.6フィート
- タイラバ:約6~7フィート
竿の曲がり方(テーパー)
- ライトジギング:ファースト~レギュラーテーパー(先~胴調子)
- タイラバ:ファースト~スローテーパー(先~胴調子)
素材
- ライトジギング:ほぼカーボン(穂先がチタンもある)
- タイラバ:ほぼカーボン(穂先がチタンやグラスもある)
自重
- ライトジギング:約110g~220g
- タイラバ:約100g~140g
適合ルアーウエイト
- ライトジギング:20g~180g
- タイラバ:30g~200g
先径
- ライトジギング:0.8mm~
- タイラバ:0.7mm~
(※マイボ!調べ。すべてのメーカーの全商品がこの仕様に該当するわけではありません)
以上のように割とスペック的には似ているように見えます。
ただ平均値を見るとやはりライトジギングの方がパワーがあるロッドが多く、具体的には以下のような感じ。
タイラバロッドよりライトジギングロッドの方が…
- 自重重め
- 適合ルアーウェイト重め
- 先径太め
ライトジギングとはいえ対象魚が青物や根魚も含まれるためある程度力負けしないパワーを持たせている仕様になっていますね。
特に先径は上記の表では最低の細さで見ているため差はほとんどないように見えますが、平均的にはタイラバロッドの方がかなり細いです。

タイラバはジギングのようなアクションが不要で、ただ巻き時の穂先感度アップに特化できるため可能な仕様なのでしょう
その他長さや適合ルアーウェイトなど、使用するフィールドや状況によって異なるため一概には言えませんが、ライトジギングタックルの中でもできるだけライトなモデルを選択すればタイラバロッドに近くなります。
リールの違い
続いてライトジギングとタイラバリールの違いについて。
最大ドラグ力
- ライトジギング:5~7kg
- タイラバ:3~7kg
自重
- ライトジギング:220~350g
- タイラバ:185~300g
ハンドル形状
- ライトジギング:シングル、ノブサイズ大きめ
- タイラバ:ダブル、ノブサイズ小さめ
ギア比(最大巻上長)
- ライトジギング:4.9(55cm)~8.1(81cm)
- タイラバ:4.9(52cm)~7.8(78cm)
(※マイボ!調べ。すべてのメーカーの全商品がこの仕様に該当するわけではありません)
ライトジギングもタイラバも丸型かロープロ型の2種類のリール形状があります。
どちらを選択するかで自重やドラグ力が変わってきますが、それはライトジギングもタイラバも同条件。
同じ丸型または同じロープロ型と条件を揃えて比較するとスペック的にはよく似ています。
タイラバリールよりライトジギングリールの方が…
- 自重重い
- シングルハンドルでサイズ大きい
- ギヤ比高め
やはりタイラバリールの方が全体的に小型でライトなイメージ。
ただ自重やドラグ力などの差はそこまで大きくないのに対し、ハンドル形状の差が大きいですね。
タイラバはダブルハンドルで小さなノブが主流であるのに対し、ライトジギングはシングルハンドルでラウンド型やT字型など大型サイズノブのリールのラインアップが多い。
もちろんジギングというアクションを入れる釣りに合わせて握りやすい形状になっていて、逆に小型ダブルハンドルでジギングはかなりやりにくいです。
また、ギヤ比もライトジギングの方が7~8ぐらいのリールが多く全体的に高め。
これもジギングのアクションに合わせた設定になっていて、タイラバに流用する場合注意が必要です。
普段タイラバをハイギヤリールで行っている、または行いたい場合は問題ないですが、ローギヤで超スローに一定速度で巻く動作は苦手。
ライトジギングリールはハンドルサイズ大きくハイギヤである
=タイラバの速巻きは得意
以上のライトジギングリールの特性を活かしてタイラバに流用してやる必要がありますね。

ライトジギングリールを流用するタイミングはタイラバに反応が良い=速巻きでも当たってくるような状況が多く、割と自然に代用できるかも
ちなみにライトジギングにもタイラバにも兼用するには電動リールを使用するのもオススメ。
電動のルアー釣りに抵抗があるかもしれませんが、ハンドルサイズやギヤ比の違いをある程度カバーできます。
まとめ
以上ライトジギングとタイラバの違いを比較してきました。
タイラバもライトジギングの一種、という考え方もあったりするためスペックも全体的にはよく似ていました。
ただやはりジギングとタイラバではルアーアクションが違うため、それがロッドやリールスペックに表れています。
- ロッドはできるだけライトなものがよし!
- リールはハイギヤ、大きめハンドルを活かす!
- 超スロー巻きが必要な状況では難しいかも…
- 電動リールもオススメ!
以上のようにライトジギングタックルの特性を活かす、またはカバーする形であればタイラバにも代用できるという結論です。
ライトジギングしてる時に真鯛の活性が高く、タイラバに反応がイイ!
そんな時はライトジギングタックルをそのまま流用してやれば、タイラバの早巻きにも相性がイイはず。
こういう状況の時だけ使いまわす、という感じであればライトジギングタックルをタイラバに代用するのはアリでしょう!
※余談

ライトジギングもタイラバも状況問わずガッツリ使いまわしたい!
そんな方は何度もしつこいですが、やはり電動リールがオススメ。
電動ジギングや電動タイラバってゲーム性が損なわれるようなイメージありますが、電動ならではの楽しみもあります。
タイラバと兼用しやすいオススメのライトジギングタックル
最後にタイラバと兼用できるオススメのライトジギングタックルの紹介。
タイラバと兼用しやすいライトジギングロッド
まずはロッド、ダイワから3種、シマノから1種。
メインのライトジギングのフィールドや対象魚によってロッドのモデルを選ぶ必要はありますが、今回はタイラバと兼用ということでそれぞれもっともライトなモデルを選択しています。
ダイワ ブラストBJ(63HB-S・Y)
- 全長:1.91m
- 自重:135g
- 先径/元径:1.1/9.9mm
- 適合ルアー重量:30-120g
- 適合PEライン:0.6-1.2号
- 定価:26,500円
2019年新発売のベイジギング(BJ)モデル。(=ライトジギングモデルのこと)。
先径細く、自重も軽い。
適合ルアー重量や適合ラインを見ても、タイラバロッドだと言われても不思議ではないようなスペック。
高感度な穂先「メガトップ」搭載で強度もアップしており、自然にタイラバにも流用できるでしょう。
ジギングロッドと言うと割と高額なモデルが多い中で実売価格2万円を切る価格設定もありがたいですね。
ダイワ キャタリナ BJ エアポータブル(64MLS-METAL)
- 全長:1.93m
- 自重:100g
- 先径/元径:0.8/8.4mm
- 適合ルアー重量:20-60g
- 適合PEライン:0.4-0.8号
- 定価:34,000円
先ほどの「ブラストBJ TW」同じくダイワの1ランク上位モデル。
「エアポータブル」ということでセンターカット2ピースモデルで電車や車での携行がしやすくなりました。
他にもさらなる軽量化、細身化もなされ、タイラバロッドの中でもライトなモデルに近いスペックになっています。
さらに金属穂先「メタルトップ」搭載で超高感度と強度も持ち合わせています。
かなりライトなスペックでライトジギングに使える範囲は限られてくるでしょうが、タイラバロッド以上にタイラバに使えるライトジギングロッドと言っても過言でないでしょう。
ダイワ ソルティガ BJ ローレスポンス(63HB-S・V)
- 全長:1.91m
- 自重:135g
- 先径/元径:1.1/7.9mm
- 適合ルアー重量:60-120g
- 適合PEライン:0.6-1.2号
- 定価:49,000円
ダイワのジギングロッドとして最高峰の「ソルティガ」のライトジギングモデル。
先ほどの「キャタリナBJ」よりは自重重く、先径も太くなってしまいますが、その分使える範囲が広がります。
さらに「X45」「メガトップ」「HVFナノプラス」など搭載で強度や感度も最高クラス。
「ローレスポンス」モデルということでブランク全体の張りを落とすことでタイラバに流用しても「乗せ調子」として機能するでしょう。
シマノ オシアジガーLJ(B65-0/FS)
- 全長:1.96m
- 自重:127g
- 先径:1.5mm
- 適合ルアー重量:30-100g
- 適合PEライン:1.2号
- 定価:49,000円
2019年発売、シマノのジギングロッド最高峰モデル「オシアジガー」のライトジギングモデル。
今回はタイラバに流用ということで、その中でも究極にライトな「スーパーライトジギング」モデルの紹介。
適合ウェイト30g~、自重も130gを切る軽さでタイラバに自然と流用できます。
さらに「ハイパワーXフルソリッド」仕様で細さや繊細さ、粘り強さを活かしつつ、ネジレやブレも解消しています。
スーパーライトとはいえある程度の大物まで対応できる底力も持っており、ライトジギングからタイラバまで幅広く使えるでしょう。
オススメリール
続いてタイラバに流用できるライトジギングリールを2機種の紹介。
ダイワ ティエラ A IC 150H(L)
- 巻取長さ(cm):80
- ギヤ比:7.1
- 自重(g):225
- 最大ドラグ力(kg):5
- 標準巻糸量PE(号-m):1-400、2-200
- ハンドル長さ(mm):70(シングル)L
- ベアリング(ボール/ローラー):6/1
- 定価:36,300円
「ティエラ A IC」は水深や巻上スピード表示できるカウンター搭載のリール。
ライトジギングでもタイラバでもアタリのあった水深や巻上スピードが正確に分かるというのは、ヒットパターンの再現に役立ち大きな武器になります。
また、2万円台という価格帯ながら「ハイパードライブデザイン」採用されており、ロープロ型ながら強度のあるアルミフレームで頑丈、数年前ならもっとかなりの上位機種並みの性能を持ちます。
タイラバにハンドルノブLサイズは逆に使いにくい所もあるかもしれませんが、リールの性能としては万能で間違いなく、コストパフォーマンスに優れるリールです。
シマノ フォースマスター600/601
- 巻取長さ(cm):67
- ギヤ比:6.5
- 自重(g):490
- 最大ドラグ力(kg):10
- 標準巻糸量PE(号-m):2-300、3-200
- ハンドル長さ(mm):65
- ベアリング(ボール/ローラー):8/2
- 定価:95,200円
最後に電動ジギング、電動タイラバができるシマノ「フォースマスター600」。
これまで紹介したリールはすべて巻き取り長さ70cm以上あるハイギヤモデルが多く、またハンドル形状的にもタイラバの超スローな低速巻きが苦手。
ですからタイラバに流用する状況として、ある程度速いスピードの巻きで反応がある状況じゃないと使いにくい部分はありましたが、電動リールなら状況問わず兼用することができます。
特にシマノ最新の電動リールには「超微変速制御」や「タッチドライブ」搭載で超スロー巻上+速度微調整が可能。
さらに「モーター&クラッチ連動機能」でジグやタイラバをフォール→着底→巻上開始の流れでモーターを手動でON/OFFしなくてもよく、スムーズに行えます。
電動ということで自重が重いという弱点はありますが、ライトジギングでもタイラバでも電動ならではのゲーム性やいろんな釣りに使える汎用性があります。
シングルハンドルとダブルハンドルモデルの設定があり、ライトジギングとタイラバの使用頻度に合わせて選択しましょう。