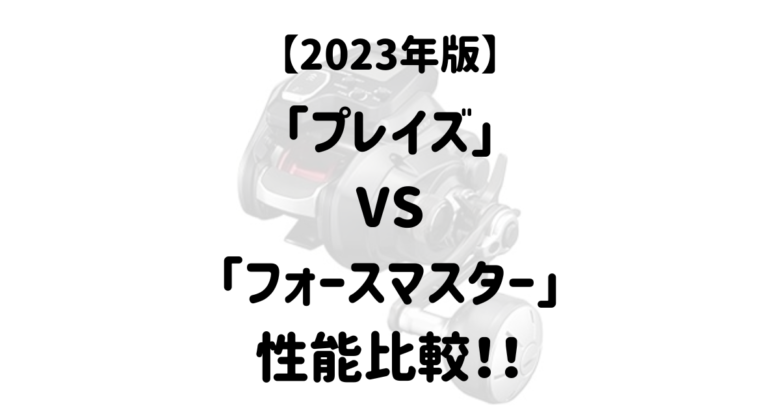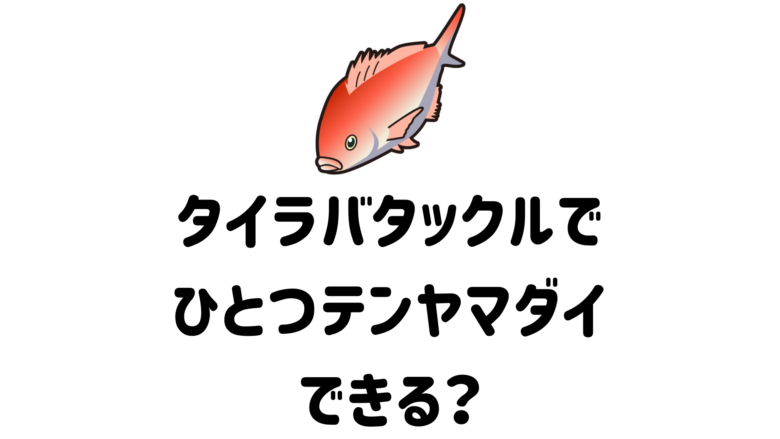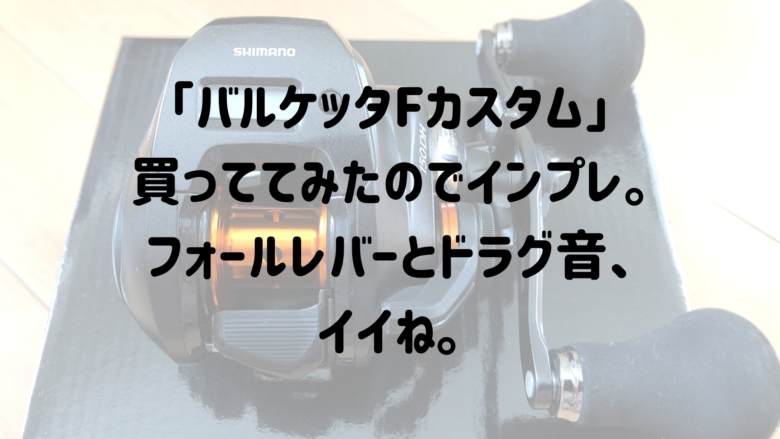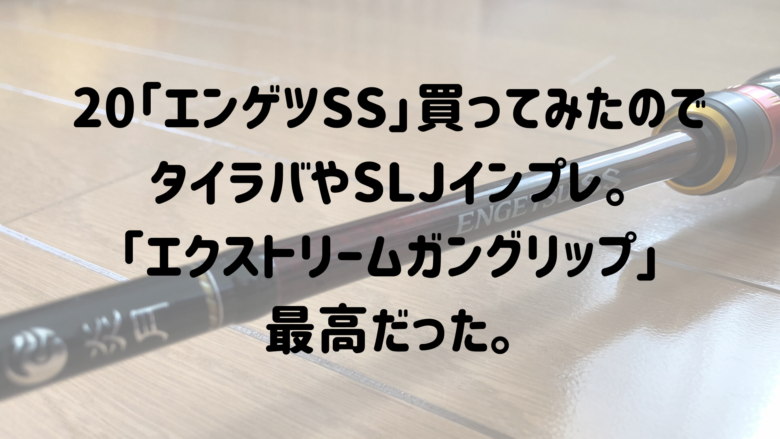タイラバリールは軽いほどイイ?メリットとデメリット解説と軽量ランキング!
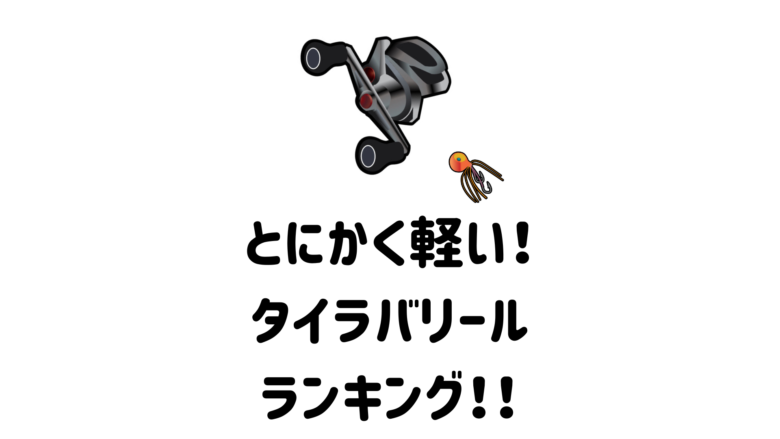
タイラバリールにおける軽さの重要性とは?
タイラバロッドやタイラバリールはダイワやシマノはじめ、いろんなメーカーからたくさんの種類が販売されています。
その中でも軽量であることを売りとしたロッドやリールが多くあり、タイラバにおいてタックルの軽さと言うのは大変重要な要素。

タイラバタックルはどうして軽いほうがいいの?

タイラバに限らないけど、タックルが軽量であることで受けられるメリットがいっぱいあるんだよ。デメリットもあるけど
ということで今回はタイラバリールが軽量であることのメリットとデメリットを解説した上で、各社タイラバリールの軽量ランキングも合わせて紹介します。
※ランキングはマイボ!調べ。僕が知ってるタイラバ専用リールを発売しているメーカー(ダイワ、シマノ、アブ、テイルウォークなど…)の中からピックアップしてみました。
タイラバリールが軽量であることのメリット
まずタイラバリールが軽量であることのメリット。
感度が良くなる
リールが軽いと魚のアタリや潮流の変化、着底時の反応などが分かりやすい、つまり感度が良くなります。

ベアリングやギアの素材など影響するため、一概に最も軽い=最も感度が良い!とは言い切れないですが…
それ以外にも組み合わせるロッドの感度や自重、ライン素材、細さなども関係しており、究極の感度を求めるとタックル全体のトータルバランスも必要になります。
しかしリールの軽さ以外のベアリングやギヤの素材などの条件を同じとして比べた場合に、重いリールと軽いリールどちらが感度が良いかと言うと、軽いリールの方が感度が良いのは間違いないでしょう。
他の釣りでも感度が良いほうがイイのでしょうが、タイラバは特に鯛のついばむような小さなアタリをとる必要がある釣り。
特に活性の低い渋い状況だとより感度の良いリールで小さなアタリを拾ってフッキングに持ち込むことができるリールじゃないと釣れないこともよくあります。
感度が劣るリールだと小さなアタリが出ていることに気付かずフォールしてしまったり、巻くのを止めてしまう事でフッキングに至らないってことも。

一日中タイラバをしていると、こんなケースをヒットに持ち込めるかどうかで釣果の差がでてくる
よってタイラバリールには感度が良くなる要素のひとつである軽量さが求められるわけです。
疲れにくい
タイラバはひたすら巻き巻きとフォールを手持ちで行う釣り。
ジギングなどアクションを必要とする釣りと比べると楽な釣りではありますが、それでも1日中手持ちでタイラバしているとロッドとリールの自重の分持ち重りしてくるものです。
これに対してリールの自重が軽ければ軽いほど疲れにくくなります。
集中力が持続する
疲れにくいから派生してくることでありますが、リールが重いと持ち重りして疲れやすい→集中力の低下につながります。
集中力が低下すると、鯛の小さなアタリを見逃してしまったり、着底後の巻きはじめが遅れるなどで根がかりの原因になったりして釣果は落ちてしまう事でしょう。
反対にリールが軽いと…
- 疲れにくい
- 集中力が持続する
- 小さなアタリや状況の変化に気づくことで釣果につながる
- 釣れたらテンションアップ
- テンション上がってさらに集中力アップ
という好循環が生まれます。
キャスティング不要のためロッドとのバランスはそこまで考えなくてもOK
キャスティングが必要かつリールの軽量さも求める釣り、例えばバス釣りだと軽量を売りとしたキャスティングベイトリールは多数存在します。
しかしバス釣りではリールがとにかく軽ければイイってもんではなく、ロッドの長さや自重とのバランスも必要。
ロッドが重いのにリールだけ極端に軽いとバランスが悪くてキャスティングしにくいということもあるので。
これに対してタイラバは基本的にはキャスティングはせず、船の真下にフォールさせる釣り。

キャスティングする場合でもアンダーハンドで軽くキャストする程度なら比較的タックルバランスは気にならない
よってリールとロッドのバランスはキャスティングが必要な釣りと比べると、そこまで意識しなくてOKです。
ただこのロッドとリールのバランスについては人それぞれ考え方が異なるかもしれません。
絶対的なものではなく感覚的なものなので、「バランスは合っている方がイイ!」逆に「そんなの考えなくてもとにかく軽量であればイイ!」といったいろんな意見、考え方あると思いますのでこれについてはご参考までに。
タイラバリールが軽量であることのデメリット
続いて反対のタイラバリールが軽量であることのデメリット。
剛性、耐久性が劣る
タイラバ専用リールとして販売されているリールはロープロファイル型と呼ばれる小型リールもたくさんあります。
その中でも特に軽量であるのは樹脂素材であるリールが多数です。

シマノの軽量カーボン素材「CI4+」とかが有名ですよね
ただ樹脂は軽いのが売りではありますが、剛性や耐久性が心配。
例の「CI4+」など、最新技術により剛性や耐久性アップしていることは間違いないですが、金属製リールと比べるとどうしても劣ります。
僕も10年以上前に購入した金属製の丸型リール(カルカッタ)がいまだに現役バリバリで使えているのを見ると、耐久性はさすが。

これだけ長年使うのは特殊かもしれませんが、リールの軽量さ(樹脂製)と耐久性、剛性(金属製)は相反する要素でどっちをとるかは永遠のテーマでしょうか
使用するタイラバ重量、フィールドとのバランスは必要
先ほどあげたメリットで、ただ巻くだけのタイラバにおいてロッドとのバランスはそこまで考えなくてもOK。という項目がありました。
ただ、使用するタイラバやフィールドとのバランスは必要かと思います。
どういうことかと言うと、200gとか重いタイラバを使用するような状況=深場や潮流の速いフィールドで極端に軽いリールだとバランスが悪く安定した等速巻きがしにくくなります。
また、軽いリールは全般的に最大ドラグ力などパワーが劣るため潮流が速いポイントで大鯛がかかると巻上も大変。

ですからこういったポイントではタックルが軽ければイイってものではなく、パワーがあるリール=金属製の丸型リールを選択した方が安心
まとめ
ということでタイラバにおいてリールが軽量であることのメリットとデメリットをまとめてみた。
- タイラバにおいてリールは軽ければ軽いほど有利
- ただしパワーが必要な激流ポイントや大物相手だと苦しい
- 重い金属製リールと比べると剛性や耐久性は劣る
よって釣行するフィールドに水深が100mを超えるような極端な深場や、玄界灘や海峡などの激流ポイント、また大鯛や大型青物がよく掛かってくるようなポイントでない限りは上記メリットがあるため軽量リールが有利ということですね。
あとは耐久性をどうみるか。
耐久性が高いリール=金属製の丸型リールの選択になるため、デザインやグリップ感なども含めお好みで選びましょう。

ロープロ型と丸型リールの違いなどについては別記事でまとめてみた
軽量タイラバリールランキング!
では最後にタイラバ専用として販売されている各社リールの軽量ランキング!ベスト3を集計してみました。
ただ軽けりゃいい!ってもんではなく金額やその他スペックも重要ではあります。
ランクインしたリール3機種は大きな差はないため、軽量なリールを探している場合はこれら3機種の中から選べばOK。
あとはそれぞれ個性があるため、金額やその他スペック、デザインなどで決めましょう!
第3位 ダイワ「紅牙」自重205g
100(右巻)/100L(左巻)
- 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):63
- ギヤ比:63
- 標準自重:205
- 最大ドラグ力:5.5
- 標準巻糸量PE(号-m):0.8-400 , 1-300
- ハンドル長さ(mm):130
- ベアリング(ボール/ローラー):5/1
- メーカー希望本体価格(円):31,400
100XH(右巻)/101XHL(左巻)
- 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):81
- ギヤ比:8.1
- 標準自重:205
- 最大ドラグ力:5.5
- 標準巻糸量PE(号-m):0.8-400 , 1-300
- ハンドル長さ(mm):130
- ベアリング(ボール/ローラー):5/1
- メーカー希望本体価格(円):31,400
まず第3位は2023年モデル、ダイワのミドルクラス「紅牙」の最大の売りは「HYPERDRIVEデザイン」。
なんともすごそうなネーミングですが、滑らかで高耐久なギアシステム(ハイパードライブデジギア)や高強度な金属(アルミ)フレーム(ハイパーアームドハウジング)、そして固着しにくく高耐久なクラッチシステム(ハイパータフクラッチ)など、高い基本性能を長年維持するための技術です。
他にも滑らかに追従しながら効き続けるドラグシステム「ATD」や軽く等速巻きしやすい「130mmロングハンドル」など最新モデルならではの性能。
そして205gと軽量。
じっくりタイラバをやり込みたい!という方にオススメ。
第2位 シマノ「エンゲツBB」自重200g
100PG(右巻)/101PG(左巻)
- ギア比:5.5
- 最大ドラグ力(kg):6
- 自重(g):200
- 糸巻量PE(号ーm):1-200
- 最大巻上長(cm/ハンドル1回転):55
- ベアリング数 S A-RB/ローラー:4/1
- 定価(円):17,500
100HG(右巻)101HG(左巻)
- ギア比:7.2
- 最大ドラグ力(kg):5
- 自重(g):200
- 糸巻量PE(号ーm):1-200
- 最大巻上長(cm/ハンドル1回転):72
- ベアリング数 S A-RB/ローラー:4/1
- 定価(円):17,500
2022年発売、シマノ製タイラバ専用リールの中では最安、最軽量のリール。
軽いだけでなく、金属(アルミ)フレームの「HAGANEボディ」採用で耐久性と剛性も確保。
安いながらも最低限の機能は備えていてコストパフォーマンスに優れた「エンゲツBB」、初心者の方や予備機にもオススメ。
第1位 アブガルシア「REVO TRV」自重187g
- 自重(g):187
- ギア比:6.4
- 最大ライン巻取(cm/ハンドル1回転):64
- 最大ドラグ力(kg):5.5
- PE糸巻量(号ーm):1-200
- ボール/ローラーベアリング:5/1
- 定価(円):25,000
軽量タイラバリール第3位は、アブガルシアのタイラバ専用リール「REVO TRV」。
187gで軽量でありながらアルミニウム製フレームで一定の剛性や耐久性も兼ね備えています。
また「REVO TRV」の売りは120mmというロングハンドル。
等速巻きしやすく、また、突然のヒット時やボートが揺れたりした時もハンドルから手が離れにくいです。
最大ドラグ力5.5kg、ボールベアリングも5個搭載しており、タイラバ用リールとして基本性能も問題なしでしょう。
他にはドラグクリッカー、ソフトクラッチ、インフィニブレーキシステムなど搭載しており、タイラバで活躍する機能たくさん。
軽量であることも大きな武器ですが、その他性能が充実していながら低価格とお買い得なリール。
以上タイラバリール軽量ランキングでした!
とにかく軽いタイラバリール探してる!方のお手伝いになれば幸いです。。。